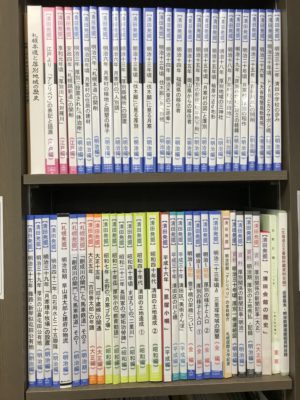あしりべつ郷土館で清田区の歴史を学ぶ 清田高校生 韓国語で清田の歴史を発表へ
あしりべつ郷土館(札幌市清田区清田1条2丁目、清田区民センター2階)に10月29日(金)、清田高校生4人が訪れ、館内の展示物を見学し、清田区の歴史を学びました。
 この高校生は、清田高校で韓国語を学んでいる3年生で、全員が清田区在住だそうです。この日は同高校で韓国語を教える非常勤講師の高野康夫先生(ことばサポーターなぐね代表)に引率されて来館しました。
この高校生は、清田高校で韓国語を学んでいる3年生で、全員が清田区在住だそうです。この日は同高校で韓国語を教える非常勤講師の高野康夫先生(ことばサポーターなぐね代表)に引率されて来館しました。
生徒たちは、韓国語で地元清田区の歴史をまとめ、卒業前に韓国語で清田区の歴史を発表するそうです。
 生徒たちは、館内に展示されている昔の農機具や生活道具などを興味深そうに見学し、写真を撮っていました。
生徒たちは、館内に展示されている昔の農機具や生活道具などを興味深そうに見学し、写真を撮っていました。
また、あしりべつ郷土館のボランティア・スタッフ3名から、次のような明治の開拓期から昭和までの清田区の歴史の話を聞きました。
〇昔、今の清田区地域は「あしりべつ」という地名だった(昭和19年に清田、北野、平岡、真栄、里塚等の地名に変更)
〇今の清田区に明治6年(1873年)、最初に入植した開拓者長岡重治氏の話
〇国道36号線の基になった明治6年(1873年)の札幌本道造成と「旧道」の話
〇明治25年(1892年)に「吉田用水」という灌漑用水路が造成され清田に水田が広がった話。吉田用水の記念碑がコカ・コーラの裏にあること、吉田用水の跡が今も北野に残っていること
〇清田区に電気がともったのは昭和19年(1944年)で、それまではランプ生活だったこと
〇昭和40年代から宅地化が進み、農地が急速に減っていったこと、特に昭和の終わりから平成にかけて急速に住宅地が広がり、今の街並みになったこと
〇こうして人口が増え、平成9年(1997年)に豊平区から分区して清田区が誕生したこと
 あしりべつ郷土館は、清田区内の町内会員1世帯年間40円の負担で運営しています。施設は市からの無償提供で、運営は清田区内の町内会連合会でつくる郷土館運営委員会が行っています。
あしりべつ郷土館は、清田区内の町内会員1世帯年間40円の負担で運営しています。施設は市からの無償提供で、運営は清田区内の町内会連合会でつくる郷土館運営委員会が行っています。

清田区の歴史を紹介した動画も視聴
昔の農機具や生活道具、写真の展示のほか、地元の郷土史家・了寛紀明氏(里塚在住、元清田小学校校長、あしりべつ郷土館スタッフ)が調べた清田区の郷土史の資料が数多く展示されています。展示物はすべてかつて清田区で実際に使われていた貴重なもので、区民からの寄贈です。
開館日は水曜日と土曜日で開館時間は10時~16時です。入館は無料です。ホームページもあります。ぜひ、ご覧になってください。
開館日以外でも、団体見学の申し込みがあれば開館し、ガイドも行います。あしりべつ郷土館の公式ホームページから申込できます。
「ひろまある清田」より転載